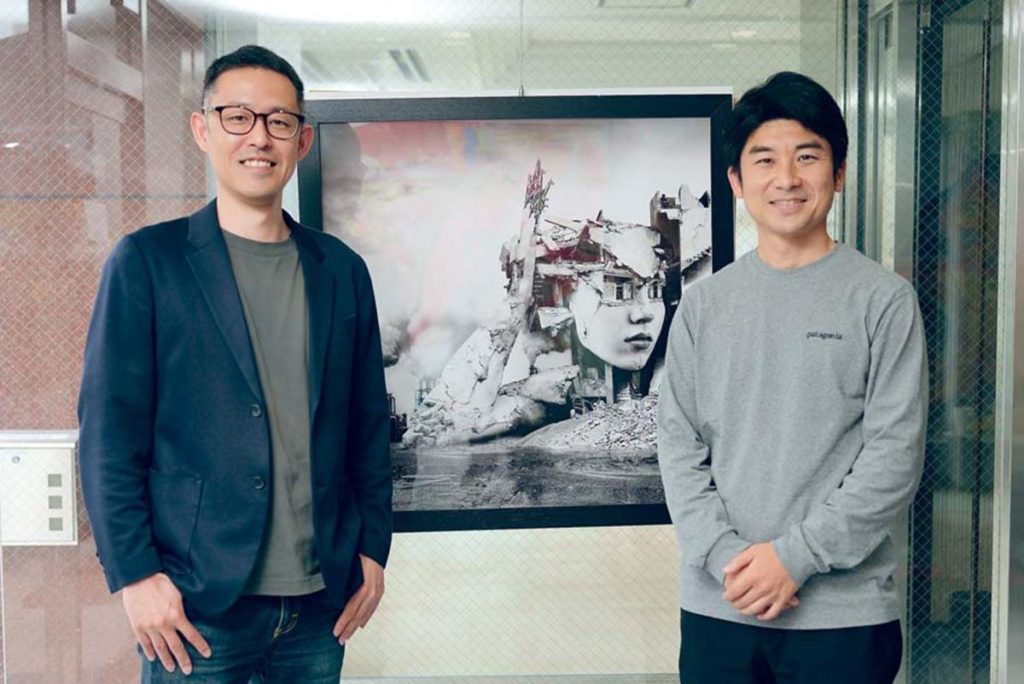
「『社会貢献』は、儲かってから行うもの」。一昔前の起業家界隈では、当たり前のように、そう言われていた。このパラダイムが主流だった2005年に、あえて「ソーシャルビジネスしかやらない会社」として創業したのが、ボーダレス・ジャパンだ。同社は今や、世界16カ国で46を超えるソーシャルビジネスを展開し、グループ年商は65億円を超える(2022年7月現在)。ボーダレス・ジャパンが提供する社会起業家のためのプラットフォームは、社会の不条理や欠陥から生じる社会課題をビジネスで解決しようと奮闘する起業家たちが、資金、スキル、ノウハウを共有し、相互に支え合う場となっている。
「社会のため、人のために何かしたい」との想いを抱く「普通の人」が、孤立せずにアクションを起こせる仕組みがあり、成功した起業家は「恩送り」の思想でまた新たなソーシャルビジネスを支援する。より良い社会づくりのため、そんなエコシステムの形成に人生をかける田口一成社長と鈴木雅剛副社長に話を聞いた。

田口一成
1980年生まれ。福岡県出身。大学2年時に栄養失調でおなかが膨らんだ海外の子どもの映像を見て貧困問題を知り、「この解決にこそ人生をかける価値がある」と決意。早稲田大学在学中に米国ワシントン大学へビジネス留学。2005年25歳でボーダレス・ジャパンを創業。

鈴木雅剛
1979年生まれ。山口県出身。2004年横浜国立大学大学院修了、経営学修士(MBA)取得。同年、株式会社ミスミ入社。「世界で一番働きたい会社をつくる」という思いを持つなかで田口と出会い意気投合。ボーダレス・ジャパンを共同経営。
―まずは、100年後の人類に向けて自己紹介をお願いします。
田口: 100年後の皆さん、ボーダレス・ジャパン(以下、ボーダレス)の田口一成です。21世紀初頭の社会は、社会的な課題に対する強烈な問題意識と社会変革への並外れたパワーを持つ起業家しか事業を立ち上げられない時代でした。でも、当時から「何か社会に役に立つことをしたい」という想いを持つ人たちは数多くいました。そんな「普通の人」たちが何かアクションを起こしたいと考えたときに、たとえお金がなくても、その想いを形にできる「仕組み」を作ろうと挑戦しているのが、私たちボーダレスです。現在は、「恩送りのエコシステム」という仕組みを実践しているところです。100年後に住む皆さんにとっては、誰もが当たり前にアクションを起こせる世界になっていて、「100年前の社会では、そんなこともできなかったのか!」と、いま驚きの目で見てくれていたら、嬉しいです。
鈴木:ボーダレス・ジャパンの鈴木雅剛です。田口の自己紹介にすべてが内包されていますが、少し加えるとすれば、100年前の人々は心に余裕がなく、周りの人が困っていても手を差し伸べたり、自分から行動を起こしたりすることがなかなかできませんでした。そんな時代に社会起業家を増やそうと、ボーダレスは起業家を支える仕組みづくりをしてきました。100年後には多分、もっと人と人とが助け合ったり、想いを寄せて共に生きたりしていると思います。そんな社会を願って、一生懸命頑張っていた人たちです。
-今でこそSDGsやESG投資などのメガトレンドとともにソーシャルビジネスの認知も高まってきました。2005年の設立当時はまだまだ社会の認識も薄かったのではないでしょうか。
田口:時代の風潮は変わりましたね。当時は、「『社会のために』は、儲かってから言うもの」という大前提が色濃くありました。そんな時代に社会性一本で事業を立ち上げ、20年が経ち、今や社会性がないビジネスは評価されない時代になりましたから。

-田口さんは、創業期に「ボーダレスハウス」(多文化共生を目指し外国人と国際交流ができるシェアハウス事業)をはじめとする数々のソーシャルビジネスを立ち上げ、グループ年商65億円超へと成長を遂げました。“普通”の人でもソーシャルビジネスを始められる仕組みを今も作り続けている。そのような「社会実験の場」とも言えるボーダレスという存在を100年後にも残したいと思われますか?
田口:形にこだわりはないですね。「誰かから助けてもらったから今度は自分が助けよう」とアクションを起こせる、人々が孤立せずにつながり合えるような仕組みが、脈々とつながっていけばいい。その仕組みを運営、実行できるエコシステムは、それこそボーダレスだけじゃなくて何千何万とあったほうがいいですよね。そのうちの一つとしてボーダレスが残るならそれでもいいし、どちらでもいいという感覚ですね。
―ボーダレスと言えば「恩送りの仕組み」が特徴的ですよね。グループの起業家たちの会社が黒字になれば余剰利益をグループの共通ポケットに入れ、その資金で新しいソーシャルビジネスの起業家を支援するという、その仕組みが機能しているからこそ、高確率でソーシャルビジネスを成功に導くことができるということなのでしょうか。
田口:仕組みが機能しているからというより、諦めずに挑戦できるから成功できるのだと思います。多くの場合、1回目で無理でも、2回目、3回目と挑戦すれば、成功していくわけです。僕らが作っている「恩送りのエコシステム」では、事業への投資資金は“ペイシェント・マネー”、いわゆる忍耐強いお金です。効率良くスピーディーに増やしていくお金ではなく、起業家の挑戦が花ひらくまで「我慢し続けられるお金」。創業資金1,500万円をボーダレスが提供して事業をスタートできるファイナンスの仕組みがあり、何度も再チャレンジができるので、リタイヤしてしまう人は少ないですね。
-なぜボーダレスさんに集う起業家は諦めずにトライし続けられるのでしょうか?
田口:起業の根源的な動機が「なぜ、こんなことになってるんだ!」という、憤りにあるからです。社会課題の解決を目指す事業のソーシャルコンセプトを立てるにあたり、「どんな社会課題が、何を原因に、どんな構造で起きているのだろう?」と、ものすごく深掘りしていきます。社会課題の対象についても、「これは誰の話なのか?当事者はどこにいて、どんな人なのか?」が具体的に見えてくるまで掘り下げます。そうやって、「この人たちのために頑張りたい」という輪郭がはっきりと見えてくると、問題解決に向かっての大きな推進力が働きます。メディアで社会課題がピックアップされるときなどは「社会」に目が向きがちですが、当事者がいない社会問題はないですよね。ここがしっかりしていると、事業がうまくいかないときにも「何のために事業をしているか分からない」とか、成功して「飽きる」といったマインドには陥りにくいのかもしれません。一方で、僕らは一起業家を尊重するというスタンスなので、起業家は独立独歩で経営を行います。そこに耐え得るメンタルは必要ですね。
鈴木:ソーシャルコンセプトを考えることは、社会に向き合うと同時に自分自身と向き合うことでもあります。自分のために事業をやるのか、人のために事業をやるのか。あるいは、人のためにアクションを起こした結果の見返りがあるからやるのか。自分が先か人が先かといった自分との真剣勝負を経て、明確に「人」に対してベクトルを向けられたときに、ソーシャルコンセプトの真髄が形成されるのだと思います。ただやっぱり、1人でこれをやるのは寂しいし、苦しくなりますよね。だからこそ、そんな起業家を支援するのがボーダレスの役割だと思っています。似たような困難にぶち当たったことのある仲間や、少し先のフェーズにいる先輩が近くにいれば、「助けて」とSOSを出しやすいですから。皆が「もっといい社会をつくろうよ」という強い想いを持っているので、そういう意味での「同質性」がこの小さなコミュニティには重要ですよね。応援してくれる仲間がいるからこそ、ギリギリの状況でも耐え抜ける。それがリタイヤする人が少ない理由のひとつかもしれませんね。

―では、「良い社会づくりをしよう」という想いがベースにあり、自ら解決したい社会課題が見つかったとして、それを深く「自分ごと」として捉える動機はどのように生まれてくるのでしょうか?
田口:たとえば、自分や家族のことに関しては無関心ではいられないですよね。「無関心は良くない」とよく言われますが、無関心になりがちなのは、自分から遠く「関係ない」と思っているから。これに対して、僕らのように社会に何かアクションを起こそうとするソーシャルビジネスの世界では、自分と直接的につながりのない事柄に対しても関心を向けていきます。当事者ではない自分が、仮に当事者の境遇を本当に理解できていなかったとしても、「私がやってみようかな」と興味を持ってみる。このように、にわかな興味で誰でも行動を起こせる仕組みがあり、自分と直接の関係がないことにも興味を持てる人が増えていけば、「無関心じゃない社会」になっていくと思うのです。
-確かに、自分ごとになりきっていないことには尻込みしがちですが、やってみることで変わることもありますね。
田口:やる前から踏みとどまるより、にわかでも知ろうとする関心の持ち方が、実は大切なんじゃないかと思っていて。「やるからには責任を取る」みたいなケジメも必要もない。完璧ではないかもしれないけど、やらないよりはやったほうがいいし、課題に関心を持って助けに来てくれる人は多いほうがいい。ただし、やるからには失礼のないように。ソーシャルコンセプトをこれでもかというほど深掘りして考え抜くことが、取り組む上での礼儀だと思っています。